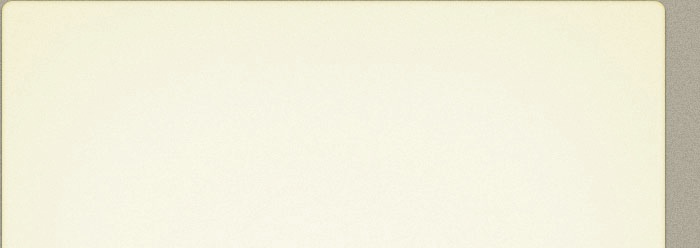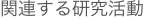【関連する研究活動について紹介します】
(『ベトナムの社会と文化』5/6合併号より転載)
「百越の会」
(国立民族学博物館にて開催)
第1回「(仮称)インドシナ研究会」(2002年2月23日、於・国立民族学博物館)
樫永真佐夫「ベトナムの人口調査における住民分類」
第2回「(仮称)百越の会」(2002年3月30日、於・国立民族学博物館)
比留間洋一「ベトナムの幼児は家庭のしつけでどう育つか-発達観、discursive practices、しつけから」
「百越の会」
第1回(2003年5月17日、於・国立民族学博物館)
中田友子「縁組みをめぐる慣習の競合について-南ラオス・ンゲの村を例に」
樫永真佐夫「ターイ親族研究文献解題」
第2回(2003年6月17日、於・国立民族学博物館)
地域研究企画交流センター・東南アジア研究センター・アジアアフリカ地域研究研究 科連携研究「地域連関の構図」研究会との共催
話題提供:ファム・スアン・グエン(Pham Xuan Nguyen)「最近の文学作品が語るベトナム政治社会の変容」
(通訳:森スアン)
第3回(2003年7月5日、於・国立民族学博物館)
伊藤まりこ「聖職者の<語り>に表出するホー・チ・ミン-カオダイ教・ハノイ聖室の事例から」
吉本康子「チャムの機織りについて-ビントゥアン省バクビン県におけるチャム族の経済・社会・文化に関する研究の中間報告」
文献紹介:蓮田隆志 Dinh Khac Thuan 2001 "Qua Thu Tich va Van Bia" Ha Noi:NxbKHXH.
第4回(2003年10月11日、於・国立民族学博物館)
比留間洋一「クメールクロム研究文献解題」
樫永真佐夫「ターイの昆虫食-ベトナム西北地方の事例」
第5回(2003年11月1日、於:国立民族学博物館)
松井生子「ラオカイ省高地の定期市研究の可能性:バックハーの事例から」
第6回(2003年12月6日、於・国立民族学博物館)
発表者:中村真里絵「タイの農村工業研究序説」
第7回(2004年1月17日、於・国立民族学博物館)
比留間 洋一「ベトナムの村の暮らしと子どもの自然利用-紅河デルタ農村の事例」
第8回(2004年4月24日、於・国立民族学博物館)
鈴木伸二「ベトナムのエビ生産コストはなぜ高くなるのか?-制度・言説・移民」
第9回(2004年5月8日、於・国立民族学博物館)
岡田雅志「18世紀ベトナム前近代王朝の異民族認識-<儂人>の分析から」
第10回(2004年7月3日、於・国立民族学博物館)
中井潤子「ビルマのマイノリティ・ヒンドゥー教徒の宗教活動の政治性」
第11回(2005年2月5日、於・国立民族学博物館)
国立民族学博物館機関研究プロジェクト「テクスト学の構築」研究会との合同開催
樫永真佐夫「ベトナムの黒タイ村落における固有文字の継承について」
第12回(2005年4月15日、於・国立民族学博物館)
樫永真佐夫「西北ベトナムにおける民族すみ分けの現在」
ベトナム研究会
研究活動
大西和彦
ベトナム学に係わる外国人としては、日本人の研究者・留学生が現在世界最大の数を擁するといわれている 。そして、ドイモイ政策によりベトナム現地での調査・研究の門戸が徐々に開かれ、近年益々多くの日本人留学生・研究者が訪越している。彼等は、ベトナム各地において様々な分野での調査・研究に携わり、あるいはベトナム学・ベトナム語研修に取り組んでいる。
ベトナムはインド・中国2大文化圏の狭間に位置し、長い歴史と複雑な民族構成を持つなどの理由から、その研究テーマは数多く未開拓の問題も少なくない。その反面、未開拓の分野が少なくないということは、先行研究も少ないということに繋がり、そのような分野に関心を持った研究者は、資料と情報の収集・分析などに多大の努力を費やさなければならない。一方、すでに研究が進められている分野においても、研究者は主にベトナム人・フランス人研究者の研究蓄積を収集・分析・批判し、自己の研究の位置付けを試みなければならない。内容に玉石混合があるにしても、先行研究の数量は得てして膨大である。
このように、他の多くの地域研究と同様、ベトナム研究には多大の作業努力が必要である。限りある修学期間あるいはベトナム滞在時間の中で、多くの専門図書・資料・情報を知見し、収集・分析してゆくことは並大抵のことではない。さらには、研究者が関心を持つ分野・テーマにおいては、自分の専門外の知識が必要なことも往々にして生ずる。そして、ベトナム滞在中にそのような作業を纏めていく途上、それが普遍性のある科学研究であるのかどうか確認してゆくことも大切であると思われる。いずれは口頭あるいは紙上において、その研究を公表する場合が多いのであるから、その確認には自己の研究に対する他者の建設的な批評も欠かせない。しかし、日本のゼミ教室から離れベトナムに在住する日本人研究者には、研究発表・調査報告をし、聴者の意見を聞く所は必ずしも恵まれているとは言えない。
以上のような状況から、ベトナム在住の日本人研究者が一堂に会して情報交換・相互批評を行うにふさわしい場所が必要であった。
幸い2002年3月、JICA組織の一つとして、ハノイ貿易大学内に設置されたベトナム日本人材協力センター(VJCC)の事業における文化交流の双方向性を重視する観点に即して、上記の目的を達する場所を提供して頂くことができた。
2002年5月28日に在留邦人有志が初会合を開き、会を「ベトナム研究会」と命名し、活動内容とその方向性を討議した。その結果に基づき、研究・調査の中間報告、各分野の研究史、研究・調査に関する情報やノウハウ、専門図書や文献資料の書評を中心に発表・報告を行っている。日時は概ね毎月最終火曜日午後であるが、参加者の帰国やフィールド調査出向が重なることなどにより隔月になったり、あるいは長期休会となったりもする。参加者は最多22名、最少7名で、常時10名前後である。
ともあれ、初会合以来2年を経て、回数は16回を数えた。以下、日時・会場・報告者・テーマの順に活動内容を列記する。
日時 2002年5月28日(火)14:00〜17:00
会場 ベトナム日本人材協力センター内セミナー室
話題 ベトナム研究会の活動内容と方向性
日時 2002年6月25日(火)14:00〜17:00
会場 ベトナム日本人材協力センター内セミナー室
報告者とテーマ
大西和彦 (フリーランス)
「ベトナム道教研究史小論」
小松みゆき(フリーランス)
「残された家族の戦後」
日時 2002年7月24日(火)14:00〜17:00
会場 ベトナム日本人材協力センター内セミナー室
報告者とテーマ
平野裕子(上智大学大学院)
「ベトナム考古学-考古社会学への一視点」
加藤敦典(大阪大学大学院)
「ベトナムにおける民主の問題について」
日時 2002年8月27日(火)14:00〜17:00
会場 ベトナム日本人材協力センター内セミナー室
報告者とテーマ
樫永真佐夫(国立民族学博物館)
「ベトナムにおける現地調査の現状」
Lee Kang Woo (ハノイ社会人文科学大学大学院)
“DNNN trong the^i ku´ §aei Mi´i(1986 - Nay)”(「ドイモイ期における国営企業(1986
年〜現在)」)
日時 2002年9月24日(火)14:00〜17:00
会場 ベトナム日本人材協力センター内セミナー室
報告者とテーマ
扇野 竜(東京大学大学院)
「ベトナムにおける労働力移動-1990年代を中心に」
日時 2002年10月29日(火)14:00〜17:00
会場 ベトナム日本人材協力センター内セミナー室
報告者とテーマ
岡田雅志(大阪大学大学院)
「18世紀ベトナム・タイバックの歴史形成-黄公質(Hoμng C《ng ChE^t)の研究史」
中島美扇(東京大学大学院)
「家譜『阮曰族歴代祖宗派支世系.』研究」
日時 2002年11月26 日(火)14:00〜17:00
会場 ベトナム日本人材協力センター内セミナー室
報告者とテーマ
川越道子(大阪大学大学院)
「ベトナムにおける戦争の記憶-死者を弔うという実践をめぐって」
日時 2002年12月19日(火)14:00〜17:00
会場 ベトナム日本人材協力センター内セミナー室
報告者とテーマ
樫永真佐夫(国立民族学博物館)
「黒タイ親族研究概論」
日時 2003年2月25日(火)14:00〜17:00
会場 ベトナム日本人材協力センター内セミナー室
報告者とテーマ
西野範子(金沢大学大学院)
「窯業村の行商史-バクニン省フーラン村を中心として」
日時 2003年3月25日(火)14:00〜17:00
会場 ベトナム日本人材協力センター内セミナー室
報告者とテーマ
大西和彦(ベトナム日本人材協力センター)
「ベトナム民間信仰文献と道教-道教経典系雷神名の記載をめぐって」
日時 2003年10月28日(火)14:00〜17:00
会場 ベトナム日本人材協力センター内セミナー室
報告者とテーマ
福田康男(ハノイ社会人文科学大学大学院)
「『ムオン族』を読んで-ベトナム語訳版より要点のまとめ」
日時 2003年11月25日(火)14:00〜17:00
会場 ベトナム日本人材協力センター内セミナー室
報告者とテーマ
扇野 竜(東京大学大学院)
「貧困削減への一考察-タイビン省農村における労働力移動に関する調査報告(2003年3
月から2003年9月実施)‐」
日時 2004年1月27日(火)14:00〜17:00
会場 ベトナム日本人材協力センター内セミナー室
報告者とテーマ
加藤敦典(大阪大学大学院)
「ブイ・ズオン・リックの『乂安記』を読む-18世紀後半のゲティン地方誌」
日時 2004年3月30日(火)14:00〜17:00
会場 ベトナム日本人材協力センター内セミナー室
報告者とテーマ
大西和彦(日本ベトナム文化交流協会ハノイ事務所・日本語センター)
「書評:グェン・ズイー・ヒン著『ベトナム人と道教』」
日時 2004年4月27日(火)14:00〜17:00
会場 ベトナム日本人材協力センター内セミナー室
報告者とテーマ
福田康男(ハノイ社会人文科学大学大学院)
「キュイジニエ以降のムオン族研究」
日時 2004年5月18日(火)14:00〜17:00
会場 ベトナム日本人材協力センター内セミナー室
報告者とテーマ
設楽澄子(一橋大学大学院)
「ドイモイ以降の農民組織(新タイプ合作社)と野菜流通について-ハノイ近郊の「安全
野菜」栽培2農村の比較調査報告‐」
以上のような、多様な発表者とテーマによって、毎回活発な議論が行われ、知識の共有と論理構築の練磨が行われている。
本稿末尾となるが、本会設立に当たり多大な御支援を頂いた初代ベトナム日本人材協力センター所長の堀添勝身氏、同初代事業調整員の木村弘則氏、同初代ビジネスコース専門指導員の細川史郎氏、並びに本会維持に多大な御支援を頂いている現ベトナム日本人材協力センター所長の橋本明彦氏、同現事業調整員の乙黒令子氏に深甚の謝意を表したい。